DV(ドメスティックバイオレンス)とは?
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、「配偶者からの暴力」のことで、夫婦間や恋人間など「親密な関係にあるパートナーからの暴力」のことをいいます。
DVがある関係は、対等ではなく、暴力を使って相手を支配する「力と支配の関係」です。
加害者は、暴力を繰り返しながら、相手の言い分を抑え込み、自分の思い通りに操りながら、相手を支配(コントロール)していきます。
配偶者とは男性・女性は問いません。事実婚や元配偶者も含まれます。
※離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受けた場合。
※生活の本拠を共にする交際相手。元生活の本拠を共にする交際相手も対象。
(交際中の恋人同士の間で起こるDVを「デートDV」といいます)
ひとくちに「暴力」といっても様々な形態が存在します。殴る、蹴るといった身体的暴力だけでなく、精神的、経済的、性的などあらゆる形の暴力があります。これらの暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起っています。
家庭内などで繰り返される暴力は、外からは発見しにくく、被害者は孤立しがちです。
DVの深刻化を防ぐには、早めの対応が大切です。
- 身体的暴力
殴る、蹴る、平手で打つ、物で殴る、髪を引っ張る、首を絞める など - 精神的暴力
怒鳴る、脅す、「死ね・何もできないやつ」等と人格を否定する など - 性的暴力
性行為の強要、避妊に協力しない など - 経済的暴力
生活費を渡さない、外で働くことを妨害する など
ひとりで悩まないで 一歩踏み出して相談してみませんか?
DV被害をはじめとした困難な問題を抱える女性への支援や各種相談窓口を掲載したパンフレットを発行しました。
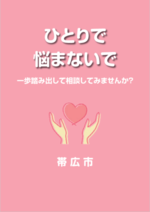
DV Q&A
Q1.夫婦げんかとDVは何が違うのですか?
夫婦げんかは、お互いが対等な立場で、それぞれの意見をぶつけ合う一時的なものであるのに対し、DVはどちらかから一方的に継続して振るわれる暴力で、力で相手を支配する関係です。
Q2.相手は優しいときもあるし、毎日暴力を振るうわけではありません。これもDVですか?
DVには、「緊張期(緊張が高まる)」「爆発期(暴力が起きる)」「解放期(優しくなる)」のサイクルがあります。このサイクルが何度も繰り返されると、徐々に暴力がエスカレートする傾向があり、支配・被支配の関係はますます強化され、次第に逃げる機会や自尊心を失い、サイクルから脱出することが難しくなります。
※全てのケースがこのサイクルに当てはまるわけではありません。
Q3.私にも悪いところがあるから暴力は起きるのでしょうか?
そうではありません。「DV防止法」では、暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるとしています。加害者から「お前がだらしないから、しつけてやってるんだ」「お前が馬鹿だから教えてやっているんだ」 などと言われることで、被害者は暴力の原因が自分にあると思いがちですが、どんな理由でも暴力は許されません。
Q4.暴力を受けることによってどんな影響がありますか?
DVは、あざや骨折といった身体的なケガだけでなく、被害者の精神面にも大きな影響を及ぼします。無力感・絶望感・うつ・PTSDなどの心理的影響や、「いつ暴力を振るわれるかわからない」という極度の緊張や恐怖から常にビクビクしたり、不眠、めまい、吐き気、胃の痛み、食欲不振、動悸など、ストレスからくる身体症状が表れることがあります。
Q5.子どもへは、どのような影響がありますか?
子ども自身が直接暴力の被害を受けなくても、子どもの面前でのDVは心理的虐待にあたり、暴力を目撃したことによって、子どもに様々な心身の症状が表れることがあります。また、暴力を目撃しながら育った子どもは、自分が育った家庭での人間関係のパターンから、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習することもあります。
Q6.暴力をふるう加害者が近づいてこられないようにしたいのですが、方法はありますか?
加害者が被害者に近寄らないようにする制度として、裁判所が加害者に発令する「保護命令制度」があります。保護命令制度には(1)被害者への接近禁止命令(被害者への電話等禁止命令、被害者の子への接近禁止命令、被害者の子への電話等禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令)(2)退去等命令があります。
保護命令は、地方裁判所へ申し立てをします。申し立てをするには、相手からの暴力等について事前に、警察署または配偶者暴力相談支援センターに相手からの暴力について事前に相談等しておく必要があります。相談等をしていない場合は、公証人役場で認証を受けた「宣誓供述書」を申立書に添付することが必要です。申し立てに必要な必要や書類の詳細は、最寄りの地方裁判所にお問い合わせください。
※宣誓供述書:公証人の前で書面に記載してあることが真実であると宣誓したうえで、署名、押印した証書のことです。
Q7.あなたやあなたの子どもに危機が迫った時は?
110番通報するか、最寄の警察署か交番に駆け込んでください。またDVによるけがをした場合、病院などの治療を受け、診断書をもらい、警察へ被害届を出すことも必要です。
参考サイト
相談窓口
ひとりで悩まずに、まずご相談ください!
帯広市役所 市民活動課 女性相談
- 平日 8時45分~17時30分
- 帯広市役所庁舎3階
- 電話:0155-65-4230(女性相談サポートライン)
帯広市役所 市民相談室「女性相談の日」
- 毎週木曜日 8時45分~17時30分
- 帯広市役所庁舎1階
- 電話:0155-65-4200
十勝総合振興局 配偶者暴力相談支援センター
- 平日 9時00分~17時00分
- 電話:0155-26-9029
帯広警察署 生活安全課
- 平日 8時45分~17時30分
- 電話:0155-25-0110
帯広警察署 緊急時
- 24時間
- 電話:110
北海道立女性相談支援センター
- 平日 9時00分~17時00分 電話・来所相談
- 平日夜間 18時00分~20時00分 電話相談
- 土曜日・日曜日・祝日 9時00分~17時00分 電話相談
- 電話:011-666-9955
- ※12月29日~1月3日は実施しません。
- ※来所相談は事前予約が必要です。
駆け込みシェルターとかち
- 平日 9時00分~17時00分
- 電話:0155-23-9911
釧路地方法務局 帯広支局
- 平日 8時30分~17時15分
- 電話:0155-24-5823
「みんなの人権110番」(全国共通人権相談ダイヤル)
- 平日 8時30分~17時15分
- 電話:0570-003-110
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部地域福祉室市民活動課男女共同参画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4134 ファクス:0155-23-0156
ご意見・お問い合わせフォーム
